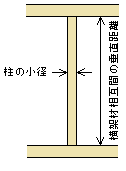
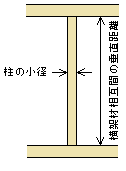
平成7年4月1日より、建築基準法施行令の柱の小径(第43条第1項及び2項ただし書)、構造耐力上必要な軸組等(第46条第2項第1号ハ、第3項ただし書及び第4項)、構造耐力上主要な部分である継手又は仕口(第47条1項)並びに 斜材・壁等の配置(第69条)等の改正に伴い、昭和56年建設省告示第1100号が大きく変更されました。
改正告示の主な内容は、木造建築物における①柱の小径基準の見直し、壁量計算の見直しによる②地震に対する必要壁量の算定基準の見直し 及び ③準耐力壁等の存在壁量への算入等が主な改正点です。
尚、この変更された告示は施行から起算して1年を経過する日までにその工事に着手する地階を除く階数が2階以下、高さが13m以下及び軒の高さが9m以下の木造建築物については、条件付きで旧規定での対応が可能と暫定措置が設けられています。
木造の建築物における柱の小径は、柱の座屈破壊を防止するため、従前は建築基準法施行令旧第43条にて、(一),土蔵造などの特に壁の重量が大きい建築物、(二),土蔵造以外の建築物で屋根を金属板・石板・木板などの軽い材料で葺いた建築物、(三),(一)及び(二)以外の建物の重量別と柱の相互間の距離及び建物の用途別と階別にて、横架材の鉛直相互間の距離に対して定数割合(1/20~1/33)にて求めた寸法以上の柱サイズが必要とされていましたが、今回の改正では定数割合を無くし、各階が負担する単位面積あたりの固定荷重と積載荷重の和を求め、下記の計算式にて求めた柱の小径以上とする事となりました。
d e / l = 0.027 + 22.5・Wd / l 2
| de | : | 柱の小径 (mm) |
| l | : | 横架材の相互間の垂直距離 (mm) |
| Wd | : | 当該階が負担する単位面積当たりの固定荷重と積載荷重の和 (N/㎡) |
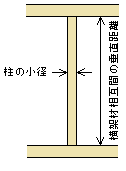
木造の建築物における構造耐力上必要な軸組等では、水平力(地震・風圧)により建物が破壊等が生じないように、従前は建築基準法施行令旧第46条にて必要壁量を壁量計算をおこなって、必要壁量以上の存在壁量をバランス良く配置するように求められ、その基本的な考え方は同様ですが、今回建設省告示第1100号の改正により、従前の地震に対する必要壁量を求めるための建物の重量種別と階数により設定されていた係数が下記の計算式により求めるように改正されました。 【旧壁量計算】参照
Lw=(Ai・Co・Σwi)/(0.0196・Afi)
| Lw | : | 単位面積あたりの必要壁量 (cm/㎡) |
| Ai | : | 層せん断力分布係数(昭和55年建設省告示第1793号第3に定める下記式により算出した数値) |
| Co | : | 標準せん断力係数 0.2 |
| Σwi | : | 当該階(当該階が3階以下の階である場合に限る。)が地震時に負担する固定荷重と積載荷重の和 (kN) |
| Afi | : | 当該階の床面積 (N/㎡) |
Ai=1+(1/-αi)・2T/(1+3T)
| Ai | : | 層せん断力分布係数 |
| αi | : | 建築物のAiを算出しようとする高さの部分が支える部分の固定荷重と積載荷重との和(建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)を当該建築物の地上部分の固定荷重と積載荷重との和で除した数値 |
| T | : | 下記の式によって計算した建築物の設計用一次固有周期 (秒) |
T=h(0.02+0.01α)
| h | : | 当該建築物の高さ (m) |
| α | : | 当該建築物のうち柱及びはりの大部分が木造又は鉄骨造である階の高さの合計のhに対する比 |
| 【告示第1793号】参照 |
改正前の規定では耐力要素として見込んでいない開口部まわりなどの垂れ壁・腰壁等(準耐力壁等)につい、壁量計算の必要壁量に算入されていませんでしたが、今回の改正では一定の耐震性への寄与が期待できることから、新たに倍率が設定され、存在壁量に算入できるようになりました。
存在壁量に算入可能な準耐力壁等は、面材、木ずり等を柱・間柱のみにくぎ打ちを施した壁と、垂れ壁及び腰壁で、具体的な構造方法の基準及び倍率の算定方法は、下記の表となります。
| 準耐力壁 | 垂れ壁・腰壁 | |
| 材料 | 面材・木ずり等 | 面材・木ずり等 |
| くぎ打ち | 柱・間柱のみにくぎ打ち | 柱・間柱のみにくぎ打ち |
| 幅 | 90cm以上 | 90cm以上かつ2m以下※ |
| 高さ | 横架材間内法寸法の80%以上※ | 36cm以上※ |
| その他 | - | 両端に耐力壁又は準耐力壁があること |
| 倍率 | 面材の準耐力壁等の倍率=材料の基準倍率×0.6× 面材の高さの合計 横架材間内法寸法 | |
| 木ずりの準耐力壁等の倍率=0.5× 木ずりの高さの合計 横架材間内法寸法 | ||
| ※ 複数の面材・木ずり等を使用する場合は、同じ材料で一続きとなっている場合に限る。 | ||
壁量計算の流れは下記流れに準じて算出し、建築物の存在壁量が必要壁量以上であることを確認します。
(1)地震力による必要壁量を求める。
(2)風圧力による必要壁量を求める。(従前と変更はありません。)
(3)各階及び方向ごとの必要壁量を決定する。
(4)存在壁量を算出する。
(5)壁量の判定をおこなう。
(6)四分割法により壁や筋かいが釣り合いよく配置されているか確認をおこなう。 【四分割法】参照
注)
壁量計算において、準耐力壁等を③準耐力壁等の存在壁量への算入に記載の条件で算入可能ですが、(6)四分割法による検証においては、存在壁量に算入する準耐力壁等の必要壁量に対する割合が、各階及び各方向いずれも1/2以下である場合は、準耐力壁等は四分割法における存在壁量に算入せず耐力壁のみで検証を行なう。ただし、存在壁量に算入する準耐力壁等の必要壁量に対する割合が、各階及び各方向いずれかで必要壁量の1/2を超える場合は、存在壁量に算入した準耐力壁等を四分割法における存在壁量に算入して検証を行うことができます。
尚、木造の建築物のうち、地階を除く階数が3で高さが13mを超え、16m以下のものにあつては、告示第1100号による計算式にて計算した各階の壁量充足率比が、それぞれ6/10以上であることを確かめなければなりません。
今回の改正において、①柱の小径基準による当該階が負担する単位面積当たりの固定荷重と積載荷重の和、並びに、②地震に対する必要壁量の算定基準よる、地震力による単位面積あたりの必要壁量の算定について、計算の複雑化が考えられ、公益財団法人 日本住宅・木材技術センターのホームページに支援用の表計算ツール、並びに早見表が公開されていますので、有効活用すると、大変たすかります。
ホーム|建築性能の基礎知識/耐震性能|木造住宅/建築基準法・構造編|旧壁量計算|四分割法|改正壁量計算|サイト・マップ